“現代演劇創造の場“俳優座劇場の静かな幕引きと不動産マネジメント
- airyflow
- 2023年7月20日
- 読了時間: 3分

大規模開発の中で
町を行き交う人たちが慣れ親しみ、思いの詰まった建築がその役目を終えていく、2023年開業の麻布台ヒルズの竣工式をはじめ、第二六本木ヒルズ(六本木5丁目西地区再開発)や、日本一高いタワー建設(大手町1丁目地区再開発)等の華やかな大規模再開発のニュースが飛び交う中、六本木交差点の近くにて、俳優座劇場(1954年開場、1980年建て替え)が、静かに幕を下ろすことを発表した。
俳優座劇場の時代
戦後、六本木界隈は、現在のミッドタウン東京等にアメリカ軍の兵士や家族が多く居住し、アメリカ軍の街として外国人向けの飲食店やショップが立ち並ぶ、国際色豊かな、エンターテイメント、ナイトライフや文化の街として発展した。その後、1954年に六本木交差点近くの現在の地に俳優座劇場が開業、1959年にテレビ朝日が開局されると、六本木の街は華やかな街へと変貌する。芸能関係者やアーティストが移り住むとともに、多くの文化人や若者達が「キャンティ」、「シシリア」や「ニコラス」をはじめ、「ザ・ハンバーガー・イン」などに詰めかけた。この様な文化的な背景の中、現代演劇創造の場として開業した俳優座劇場は、戦後の昭和、平成、令和と六本木の歴史を見守ってきたとも言える。
不動産マネジメントの視点から
企業でも行政でも、あらゆる団体は、活動の場として「不動産」を所有し、それを運用している。企業であれば、工場や本社ビル、行政なら市役所や図書館、市民ホール、市民体育館などで、これらはすべて「不動産」である。そしてこの俳優座にとっても、この劇場が不動産であった。不動産(主に建物)は最初に建てる時に多額の資金を必要とし、その後も、それを維持していくのに長期間にわたって、やはり多額の資金(ライフサイクルコスト)が必要になる。データによると、30年~50年くらいのサイクルで、建設時の費用と同程度かかってくる。ちょっとしたビルであれば、年間1億円くらいになる計算となる。しかしたいていは、毎年少しずつというよりは、20年目以降くらいになってまとめて修繕費として押し寄せてくる。それらが積もり積もって、数十億単位の修繕費が必要になってくる。ところが、たいていの団体はそういう資金の準備をしておらず、老朽化による修繕費を賄いきれず、「お手上げ」となっている。この俳優座劇場の例もその類でなかったか危惧している。すなわち、劇場そのものが終焉したというよりも、不動産のマネジメントがうまくいかなかった結果による終焉であったということはなかっただろうか。俳優座劇場が築いてきた歴史や文化は一朝一夕のものではない。それが「不動産」の問題によって終焉したとすれば、とても残念である。そして、この問題は、今、日本中のあちらこちらで見受けられる光景である。世田谷区役所(1960年竣工)や俳優座劇場と同時期に建てられた赤坂プリンスホテル(1982年竣工)等、戦後から高度成長期、そしてそれ以降に建てられた建築が、老朽化やそれに伴う維持費の高騰などを理由に取り壊されている。ただ、その一方で、日本初の超高層ビルとして知られる霞が関ビルディング(1968年竣工)は、計画的にインフラのリニューアルや維持管理等、不動産マネジメントを実施することで築55年を超えた今も現役として使用されている。また、ニューヨークにおいては、戦前に建てられたエンパイヤステートビル(1931年竣工)のような事例もある。100年コンクリートと言われる時代において、計画的な不動産マネジメントを実施することで取り壊すこと無く、利活用できる不動産は多いと考える。
俳優座劇場




俳優座劇場の隣地ですすむ再開発予定地
海外のラグジュラリーホテルが進出予定との話しも出ている
>> 活動日記一覧へ
>> コンセプト「ストック活用」




















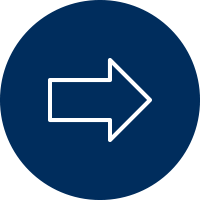
コメント